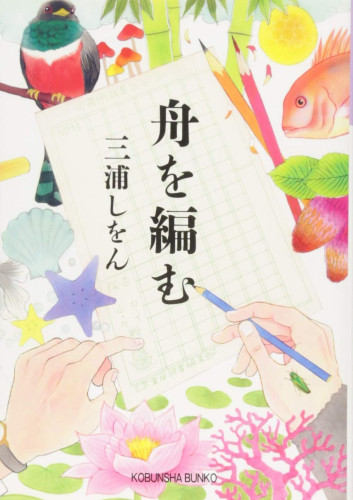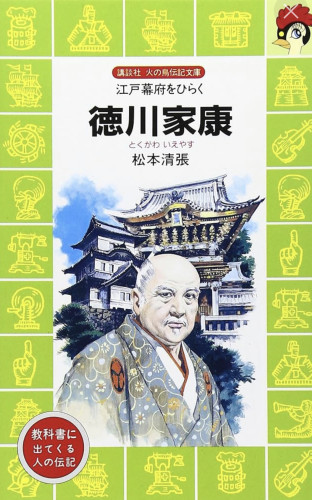ブログ
成績の良い生徒が得意なこと! (その3)
成績がいい生徒は読解力があるというお話の続きです。
音読練習の成果も出てきて、つかえずに読めるようになってきたのに、こんなお悩みはありませんか?
「うちの子、すらすら読めるようになってきたのに、内容がわかってない! いったい、どうして ⁉︎」
保護者の方にとっては、とても不思議に感じることだと思います。
すらすら読めるのに、内容がわかっていない原因は大きく3つ考えられます。
①言葉の意味を知らない。
そもそも言葉の意味を知らなければ、文の意味は読み取れませんね。
解決方法
保護者の方がお子さんに言葉の意味を確認してみて、わからない言葉があったら辞書を引いたり、保護者の方が教えたりしてみましょう。
②イメージ力が弱い。またはイメージする力がない。
言葉の意味は知っていても、それを想像するのが難しいことがあります。
イメージ力が弱いというのは、イメージすることに慣れていないため、読むことと同時にイメージすることができないケースです。
解決方法①
この場合は、読点までゆっくり読ませて、お子さんに「どういう意味?」「何て書いてある?」などと確認してあげましょう。
「読むこと=イメージすること」というのが、わかるようになれば、読みながらだんだん理解できるようになってきます。
解決方法②
低学年でイメージ力がまだ育っていない場合は、お子さんと一緒にゆっくりと文節、または読点まで読んで、その内容を説明してあげてください。
また、絵心がある方でしたら、簡単なイラストを描いてあげるのもいいでしょう。
③そもそも子どもは、自分の興味のない内容には関心を示さない。
本を読んで内容を理解できないお子さんに、親御さんが一生懸命説明しても、その説明がお子さんに届かないことがあります。
子どもは自分が興味のないことには、情報をシャットアウトする傾向があります。
大人も自分の興味のないことは、無理に聞きたくないですよね。
興味のない本を読むように無理に勧めてしまうと、読書そのものが嫌になってしまいます。
低学年で読書嫌いにしてしまうのは、あまりにも大きな損失になります。
しばらくは、好きな本や興味のある本をたくさん読むようにしましょう!!
成績の良い生徒が得意なこと! (その2)
前回のブログでは、成績のいい生徒は読解力があるとお伝えしました。
今回はその続きです。
読解力をつけるには、まずスムーズにつかえずに読めるようになることが肝所になります。
つかえずに読めるようにするには、毎日の音読練習が欠かせません。
特に低学年のうちは、保護者の方が時間をとって、音読を聞いてあげてください。
文字を読む際は、意味の区切りとなる単語や文節で間をあけますが、間のあけ方や区切り方が良かったら、褒めてあげてください。
褒めることで、お子さんはこの読み方で良かったんだ、間を空けるところも正しかったんだと理解して、ますます上手に読めるようになります。
その音読練習の時に、1つ大事なポイントがあります。
それは、速さを求めないということです。
スムーズに読むことを目指すと、どうしても速く読もうとしてしまいます。しかし、これは良くありません。
スピードは「ゆっくり」と読むことがポイントです!
スムーズに読むことと速く読むことは違います。
速く読むことを目指してしまうと、読んでも内容を理解できなくなってしまいます。
ここがとても大事です!
スピードはゆっくり!
成績の良い生徒が得意なこと!
学校で習っていないことでも、すらすら理解できてしまう人はいませんか?
自分でどんどん勉強を進めることができる人ですね。
なぜ彼らは自学ができるのでしょうか?
それは読解力があるからです。習っていないことでも、自分で教科書や参考書などを読んで理解することができるのです。
昔から「読み、書き、そろばん(計算)」と言うように、勉強は読むことから始まります。
その学年の学習内容を理解できるだけの読解力が育っていないと、勉強についていくことができなくなります。
書いてあることを読んで理解できるようになるには、大きく2つの段階があります。
第1段階は、文字をすらすら読めるようになることです。
つっかえ、つっかえ読んでいるうちは、書かれていることを理解することはできません。
それは文字を追うことで精一杯のため、内容を理解することに意識を向けられないからです。
書かれていることを、単語や文節などのまとまりで捉えられるようになると、つかえずに読めるようになります。
次回は、すらすら読めるようにするための方法と注意点をご紹介します。
三浦しをんさんの「舟を編む」がドラマ化!
読書クラス「読むとくメソッド®読書の森」の課題図書になっている三浦しをんさんの「舟を編む」を原作としたドラマが、NHK で放送されています。
この小説は 2012 年に本屋大賞を受賞し、2013 年には映画化され、その後はアニメ化もされましたので、ご覧になった方が多いかもしれません。
今回のNHKのドラマでは、ファッション雑誌の編集部に所属していた岸辺みどりが、新しい辞書「大渡海」の編纂メンバーとして辞書編集部に迎えられる様子を描いています。馬締光也をはじめ個性豊かな編纂者たちが辞書の世界に没頭し、言葉の海を渡る舟を編んでいく姿がこの作品の魅力です。
岸辺みどりを演じるのは池田エライザさん、そして馬締光也を演じるのは野田洋次郎さんです。
野田さんはロックバンドRADWIMPSのボーカルもされている異色の方です。(俳優よりも音楽の方がメインですね)
RADWIMPSは、映画「君の名は。」「天気の子」「すずめの戸締り」など数多くの作品に関わっているので皆さんご存じですよね。
NHK BSのプレミアムドラマ「舟を編む 〜私、辞書つくります〜」は、NHK BS プレミアム 4K と NHK BSで、毎週日曜日の夜 10 時〜10 時 49 分に放送されています。また再放送は NHK BS プレミアム 4K で、翌週水曜日の夜 11 時からです。全 10 話の連続ドラマです。
ぜひご覧になってください!
徳川家康の遺訓
You-Youスクールあすみが丘の授業には、子どもを本好きにする「読むとくメソッド®読書の森」という授業があります。
11月10日のブログでは、NHKの大河ドラマ「どうする家康」の話題にからめて、「読むとくメソッド®読書の森」の課題図書になっている松本清張さんが書いた『徳川家康』(講談社火の鳥文庫)をご紹介しました。
そして昨日は、ついに今年の大河ドラマ「どうする家康」がラストを迎えました。
個人的には北川景子さんの素晴らしい演技力が印象に残りました。
徳川家康は大坂の陣の翌年になくなりますが、亡くなる前に後継者へ教えを残しています。
すでにご存じの方も多いと思いますが、この教えがとても印象深いのでご紹介します。
人の一生は重荷を負て遠き道をゆくか如し
いそくへからず
不自由を常と思へばふそく無し
こころに望み起こらば困窮したる時を思ひ出すヘし
堪忍ハ無事長久の基いかりハ敵と思ヘ
勝事はかり知りて負くる事志らされハ害其身にいたる
お乃れを責て人をせむるな
及ばざるハ過ぎたるよりまされり
慶長九年卯月家康
人の一生というものは、重い荷を背負って遠い道を行くようなものだ。
急いではいけない。
不自由が当たり前と考えれば、不満は生じない。
心に欲が起きたときには、苦しかった時を思い出すことだ。
がまんすることが無事に長く安らかでいられる基礎で、怒りは敵と思いなさい。
勝つことばかり知って、負けを知らないことは危険である。
自分の行動について反省し、人の責任を攻めてはいけない。
足りないほうが、やり過ぎてしまっているよりは優れている。
(湖南市教育ネットより)
あの徳川家康でさえ、人生は思い通りにならないものだと感じていたのでしょうか。
人生において、自分を律することが何よりも大切だと伝えたかったのでしょう。
家康が亡くなって400年以上経ちますが、人の一生は変わりませんね。