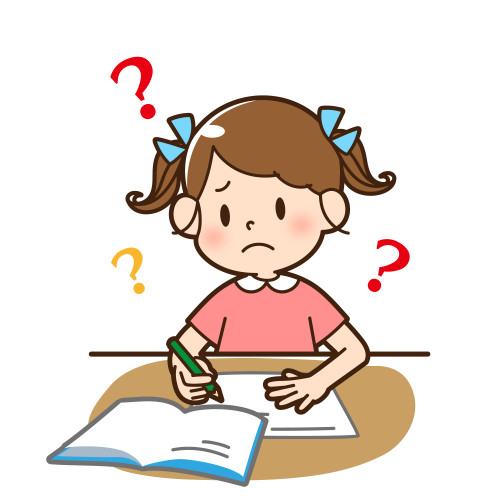ブログ
蚤の話
前回のブログでは、宿題を積極的に取り組めない生徒の話をしました。
そういう生徒によくする話があるので、今回はそれをご紹介します。
こんな話です。
Aくん、蚤(ノミ)って知ってる?
小さくて犬とか猫にくっついて血を吸う生き物。見たことある?
大きさは5㎜くらいだから、よく見ないとなかなか見つけられないかもね。
さて、その蚤なんだけど、どのくらいジャンプするか知ってる?
だいたい50㎝くらいジャンプできるんだって。
これって、かなりすごいことなんだよ。
だって人間に例えると、Aくんの身長だったら150mくらいジャンプするのと同じなんだよ。ものすごいジャンプ力じゃなない?
そんなすごいジャンプ力を持ってる蚤くんに、ちょっと意地悪をしちゃいます。
実験だからね。
蚤くんに透明なコップをひっくり返してかぶせてみます。
どうなると思う?
蚤くんはこれまで通りにジャンプするね。そうすると、どうなる?
コップの底に頭をぶつけるね。
蚤くんは自分がコップを被せられてるなんて分からないから、ジャンプする度に、何度も何度も頭をぶつけるね。ちょっとかわいそうだけど、しばらくこのままにしておきます。
だいぶ時間がたって、先生もこのままにしておくのはかわいそうだと思ったので、被せていたコップを取ってあげたの?
♪ジャジャン♪
ここで、問題です!
さて、この蚤くん、どうなったでしょうか?
やったー! コップがなくなったから、前と同じようにのびのびジャンプした。
というのは、ブッブー! 間違いです!
なんと蚤くんは、コップの底までの高さしか跳ばなくなったんだ。
どうして跳ばなくなったのかな?
かわいそうに蚤くんは、ジャンプする度に何度も何度もコップの底に頭をぶつけたから、もう高くは跳べないんだと思って跳ばなくなったんだ。
跳べるのに、跳ばなくなってしまった。
このままの状態にしていると、跳ぶための力が衰えて、本当に跳べなくなっちゃうみたいよ。
さて、先生がなんで蚤の話なんかしたと思う?
・・・
宿題をあまりやってこない生徒や、授業を一生懸命に受けない生徒には、こんな風に話をしています。
蚤くんと同じように、「自分にはできない」「これ以上無理」という考え方をしていることに、気づいてもらうために話しています。
勉強が苦手だったり(苦手と思い込んでいる)、これまでに勉強のことで嫌な思いをしたり(それを理由にして勉強ができないと思い込んでいる、もしくはそれを勉強しない言い訳にして勉強から逃げている)、子どもたちは様々なことを抱えています。
でも、どこかで自分の殻を破って「えいっ!」って思い切ってジャンプしてみなければ、状況は変わりません。
このままだと学ぶ力が弱まって、いざ学ぼうと思っても学べなくなってしまうから、そうならないように今からがんばろう、一生懸命に取り組もうということも伝えます。
Aくんなら、絶対にできるよ! だってAくんは、この蚤くんとは違うでしょう。
だからできる。一生懸命に勉強すれば、必ず成績も上がるよ!
と、言葉を掛けています。
子どもの心に、どうやってやる気の火を灯すのか?
これは永遠の課題ですね。
子ども一人ひとり琴線が違うので、色々なアプローチを試しながら子どもたちをサポートしています。
宿題をやれない生徒には…
You-Youスクールでは、基本的には宿題は自分で決めてもらっています。
そうすると、宿題の量を少なめに決める生徒が出てきます。
宿題が少ないと学習進度が遅くなったり、習ったことが定着しなかったりするので、ある程度の量に取り組んでほしいと思っています。
できる限り働きかけをしますが、残念ながら家で勉強することをめんどくさがったり、抵抗感を持っていたりする生徒もいます。
その場合は保護者の方と相談して、もうしばらくは先生の方で決めるようにすることもありますが、できれば生徒自身で決めてほしいところです。
宿題に対して、なかなか積極的になれない生徒には、色々な話をして生徒の気持ちを変えようと試みます。
そんな生徒にする話がありますので、次回のブログでご紹介します。
またまた嬉しい報告が!!
10年4か月
先週の3月8日(金)のブログで、卒業生(中3)の通塾年数をご紹介しました。
今日はその続きです。
今年の卒業生(中3)の中で、もっとも通塾年数の長い生徒は10年4か月です。
年少(3歳)から通塾が始まり、保護者の方の転勤のため途中で引っ越されましたが、また戻ってきてくれました。
あすみが丘ではない少し離れたところからの通塾だったので、送迎をされるお母さんも大変だったと思います。
お兄さんも卒業生なので、ご家族との関係は10年どころではありません。本当に感謝しかありません。
また、卒業生(中3)の半数以上が通塾5年以上です。
彼らは何年もの間いつも教室にいることが普通だったので、急に会えなくなることに気持ちの整理がつかず、私はいまだに戸惑っています。
毎年卒業する頃には、生徒にとってYou-Youスクールがセカンドハウス(第2の家)になっています。
先日、2週間ぶりに教室に来てくれた時に、卒業生(中3)に今の気持ちを聞いてみました。
入試が終わり、中3の授業がなくなって、急にYou-Youに来なくなったことについて、「何だか変な気持ち」「ずっと通いたい」「心にぽっかり穴が空いた感じ」などと答えてくれたのを聞くと、この場所が彼らにとって大事な場所だったのだと改めて思いました。
これだけ多くの卒業生(中3)が長い間通塾してくれたということは、彼らにとって居心地がよく、勉強しやすい環境だったのでしょう。
これからも、そういう塾であり続けたいと思っています。
近いうちに、卒業生に最後に書いてもらった感想文をご紹介しようと思っています。