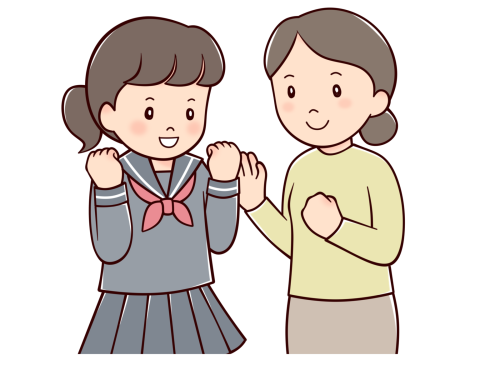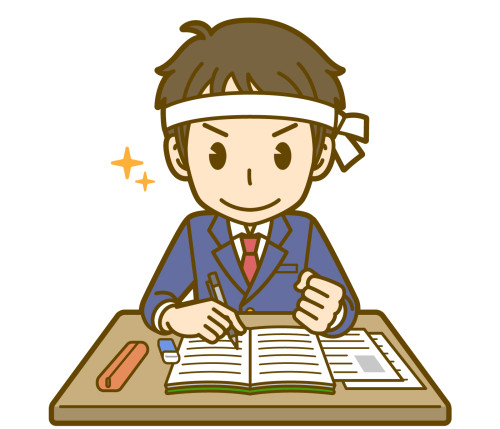ブログ
受験生の保護者ができること
受験生の保護者の皆様へ
受験を迎える子どもに、親がしてあげられることは何でしょうか?
それは、いつも通りに変わらずに過ごすことです。
保護者が行動を大きく変えると、子どもも気にします。
普段通りに過ごして見守ってください。
しかし、それでも何かしてあげたいと思うのが親心。
やってあげられることがあるとすれば、“後方支援” だけです。
【新型コロナ対策、インフルエンザ対策】
1月に入り、新型コロナもインフルエンザも同時に流行してきました。予防するには、手洗い、うがい、マスクの基本の予防対策を徹底するしかありません。家族の誰かがかると、受験生にも感染の恐れが出てきますので、家族全員で充分に気をつけましょう。
【栄養のある食事】
根菜や緑黄色野菜は強い身体を作ってくれます。朝食と夕食には、野菜がたっぷり入った豚汁やけんちん汁、鍋料理などの温かい食べ物を毎日用意してあげてください。
「まごはやさしい」(豆、ごま、海藻(わかめ)、野菜、魚、きのこ(しいたけ)、いも)を心掛けて、バランスの良い食事をお願いします。
【睡眠】
睡眠は健康な状態を維持するためには欠かすことができません。十分な睡眠は免疫力をアップします。健康でいるからこそ、勉強にも集中して取り組めます。
また、睡眠中は脳が記憶を整理して、覚えておくことと忘れてもいいことを自動的に取捨選択していると言われています。睡眠時間が短くなると、せっかく学習したことも記憶に残らないため、学習効果が低下します。毎日7時間以上の睡眠時間を確保するようにサポートしてあげてください。
子どもの話を聞く
受験生の保護者の皆様へ
公立入試まであと3週間あまりです。
受験を控えたお子さんの様子はいかがでしょうか?
多くの人は受験のような大きなイベントが近づいてくると、心が落ち着かなくなります。
普段と変わらないように見える子も、心の中では不安の嵐が吹き荒れているかもしれません。
思春期の子どもの中には、周りに自分の本当の気持ちを知られたくないと思っている子もいます。
お子さんの食欲はどうでしょうか。
睡眠は充分でしょうか。
普段と変わったことはありませんか。
弱音や自分の本心を聞いてもらえる人が近くにいると、落ち着いて過ごすことができます。
それが、友だちなのか学校の先生なのか、保護者の方なのかは分かりません。
それでも、保護者の方はいつでも話を聞いてあげられるようにしてください。
普段、自分からあまり話さないような子が話をしてきたら、家事の手を止めて向き合ってください。
よろしくお願い致します。
いつも通り
受験生の保護者の皆様へ
入試が近づいてくると、家族の皆さんも何だか落ち着かず、ソワソワしがちです。
すると、受験生の子どもに対しても、いつもと違う接し方をしてしまうことがあります。
それは悪いことではありませんが、子どもたちも普段とは違う保護者のそうした雰囲気や言動に気がつくようです。
先日も中3の受験生が、「自分はいつも通りなのに、最近、親がいつもとは違っていて、自分に気を使ってくれているんだなあと思う」と話してくれました。
受験生の子どもよりも保護者の方が浮足立って、おろおろしてしまうのもあまり良いことではありません。
保護者が心配のあまり、あれこれ口出しをするのは、受験生にとってはマイナスに働きますので十分に注意してください。
しかし、応援している率直な気持ちが子どもに上手く伝えられると、子どもにとっては何よりの勇気づけになります。
保護者の方には「いつも通り」を心掛けて、受験生のお子さんを応援していただきたいと思います。
受験生へ 復習を忘れずに
公立高校を受験する中学3年生へ
勉強は順調に進んでいますか?
まだ過去問を勉強していない人は、まずは過去問に取り組みましょう。
そして、これまでに受けた学校の実力テストや会場模試などの学力テストの直しもしましょう。
そうすると、できないところや苦手なとことが見えてくるので、教科書や学校ワークなどを使って対策をしましょう。
その時に、忘れないで欠かさずにやってほしいことがあります。
それは「復習」です。
ワークなどの問題集を取り組んだら、後で必ず復習をしましょう。
英単語を覚えたり、理科や社会の用語を覚えたときも、必ず復習をしましょう。
入試か近づいてくると、「あれもできていない、これもできていない」と、足りないところに意識が向いてしまいます。
そのため、その足りないことを少しでも多く取り組もうとします。
そんな時に忘れてしまうのが「復習」です。
新しいことをたくさん勉強するよりも、勉強したことを確実に身につけることに集中しましょう!
焦らずに、目の前のことを1つ1つていねいに取り組もう!
あなたが、持てる力をすべて発揮できるように願っています。
進路志望状況調査の結果が発表されました!
昨日、中学3年生を対象とした公立高校への進路志望状況調査(1月5日現在)が発表されました。
下記の青字の部分をタップしてご確認ください。
この数値がそのまま志願者数や志願倍率になるわけではありませんが、ある程度の動向が掴めますのでご活用ください!