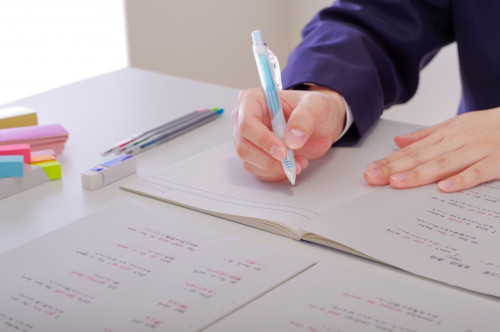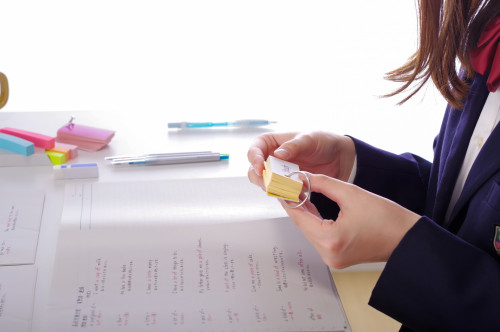ブログ
公立高校入試まであと1か月、何を勉強する?
公立高校の受験に臨む受験生へ
まだ過去問を解いていない人は、まず過去問に取り組もう!
過去問は、2回以上くり返し勉強しよう。
次に3年生になって受けた学力テストをやり直そう!
学校の実力テスト、塾で受けた学力テスト、会場模試など全ての学力テストを、こちらも2回以上取り組もう。
過去問と学力テストを勉強すると、自分の苦手な科目、苦手な単元がはっきり見えてくるので、教科書と学校のワーク、これまでに使っていた問題集などで勉強し直そう。
記述問題や英語の英作文、国語の作文などは、必ず第三者に答え合わせをしてもらおう!
記述問題の答え合わせは自分では難しいので、塾に通っていない人は、学校の先生に添削をお願いし、アドバイスをもらおう。
新しいテキストには手を付けずに、これまでに勉強したものを使って復習しよう!
不安になって、新しいものに手を出してしまうと、「あれもできない、これもできない」とますます不安になってしまうので、これまでに勉強したテキストをくり返そう。
慌てないで、目の前にあることを1つ1つていねいに取り組もう!
受験生の皆さんが、入試本番で自分の実力を発揮できるように祈っています。
自分がコントロールできることに集中する
公立高校の受験に臨む受験生へ
「よし、今日もがんばるぞ!」と勉強しようと思っても、ちょっとしたことに不安になることもあります。
例えば、友だちから「昨日は5時間勉強した」と聞けば、ちょっと焦りますよね。
「過去問で○○点取った」とか「過去問を○回くり返した」とか聞くと、不安になりますね。
そういう情報を完全にシャットアウトするのは難しいことです。
そんな話を耳にしてしまったときは、どうすればいいのでしょうか?
私たちの身の周りのことは、「自分がコントロールできること」と「コントロールできないこと」に分けることができます。
友だちの行動やその結果は、あなたがコントロールできることではありません。
友だちがどれだけ勉強するのか、テストで何点取るのかということは、あなたが直接影響を及ぼすことができないことです。
そのような、自分がコントロールできないことは、あなたが心配してもどうにもなりません。自分でコントロールできないことは、ただ受けとめるしかありません。
友だちの話を聞いてしまったら、「ああそうなんだ」と淡々と受け入れましょう。
でも、あなたがコントロールできることは、これからどのようにもできます。
自分が勉強するかしないか、どれだけ勉強するか、どのように勉強するかは、あなたが選ぶことができます。
自分がコントロールできることだけに意識と行動を集中しましょう。
自分ができることを一つひとつていねいに取り組みましょう。
そうすれば、結果は付いてきます。
がんばれ、受験生!!
令和6年度 千葉県公立高校の一般入試の日程
1か月という時間をどう捉えるのか?
公立高校の受験に臨む受験生へ
公立高校入試まであと1か月となりました。
受験生にとって、1か月という時間をどのように捉えるのかが、とても大事です。
入試まで1か月しかないと考えるのか、それとも、まだ1か月もあると考えるのか。
1か月しかないと考えると、焦る気持ちが大きくなってしまいます。
すると、気持ちがマイナスの方にどんどん傾いていきます。
「これもできてない、あれもやっていない」と、足りないところにばかり目を向けてしまい、落ち着いて勉強することができなくなっていきます。
しかし、まだ1か月もあると考えると心に余裕が生まれ、冷静に対応することができます。
例えできていないことがあっても、落ち着いて対策を考え、取り組むことができます。
そうは言っても、渦中にいる受験生にとっては、自分の気持ちをコントロールすることは、なかなか難しいことかもしれません。
そんな時はひとりで抱え込まずに、周りの人に相談してみてください。
家族、友だち、学校の先生、塾の先生…。
あなたの味方になって、話を真剣に聞いて寄り添ってくれる人が必ずいるはずです。
あなたが、持てる力をすべて発揮できるように願っています。
正攻法で取り組もう!
公立高校の受験に臨む受験生へ
私立高校入試が終わった人が多いと思います。
大半の人は、人生で初めて入試を受けたのではないでしょうか。
自分の持てる力をすべて発揮することはできましたか。
中には悔しい思いをした受験生もいるかもしれません。
本番で自分の力を発揮するのは、本当に大変です。
プロのスポーツ選手でも、試合で 100%の力を発揮するのは難しいと聞きます。
本番に慣れていない我々が、力を出し切ることは容易ではありません。
2月20日と21日に公立高校を受験する人は、どうすればいいのでしょうか。
これから1ヶ月で本番に強くなる方法は、なかなか見つからないでしょう。
ここは、正攻法しかありません。
勉強して学力そのものを高めるのです。
学力が上がれば、本番で発揮できる力は変わらなくても、得点力はアップするからです。
まだまだできることはあります。
最後まであきらめず、一緒にがんばろう!!